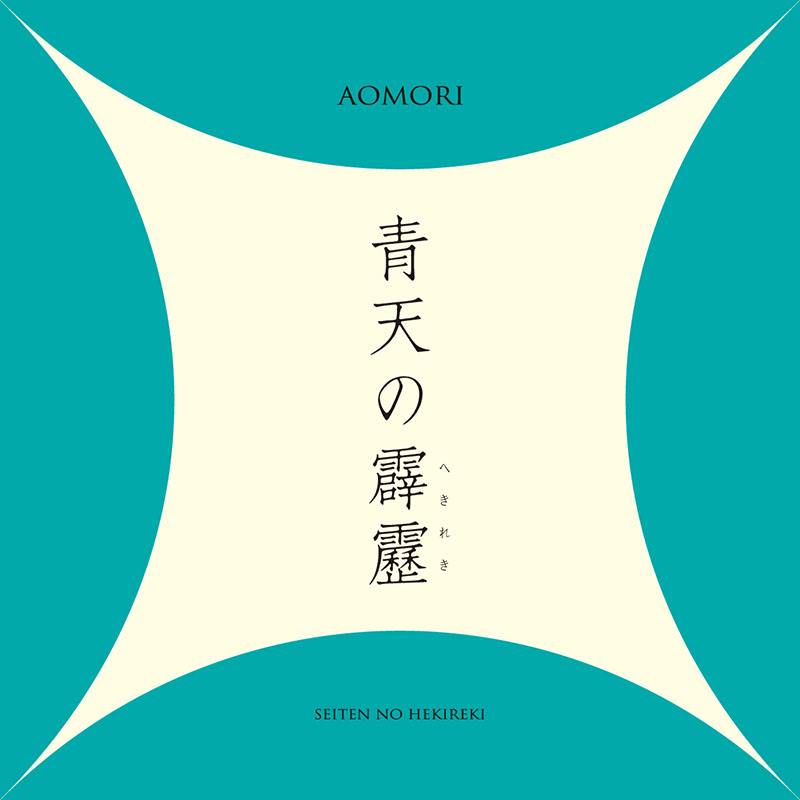
Webサイト閉鎖のお知らせ
「青天の霹靂」のWebサイトをご利用いただきありがとうございます。
アクセスされたWebサイトは 2023年3月31日を持ちまして閉鎖しました。
リンクを張っていただいている方は、お手数ですが設定を削除していただきますようお願いいたします。
あおもり産品情報サイト「青森のうまいものたち」
今後とも「青天の霹靂」をどうぞよろしくお願いします。
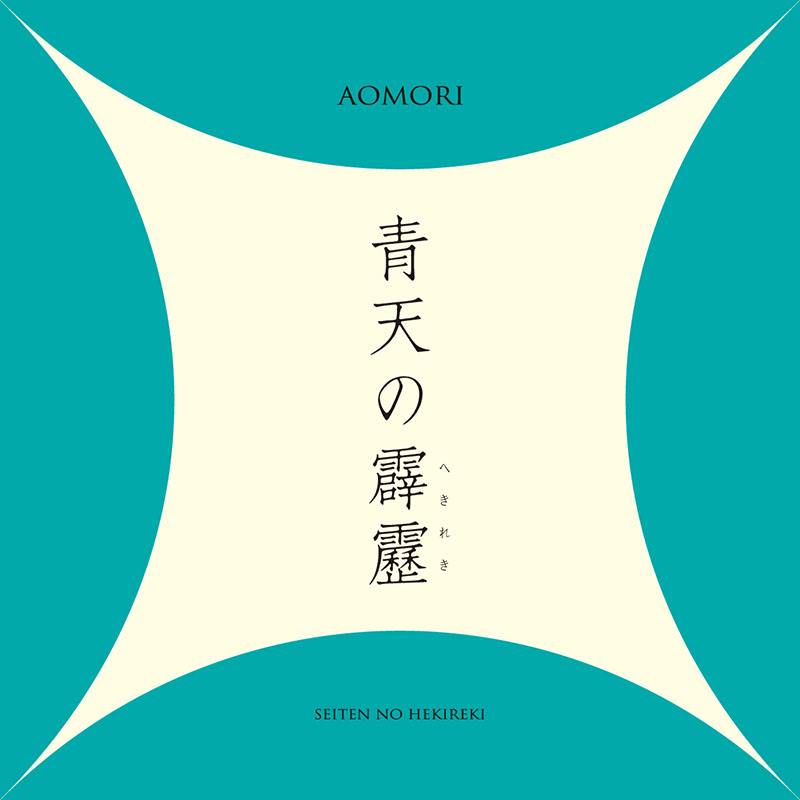
Webサイト閉鎖のお知らせ
「青天の霹靂」のWebサイトをご利用いただきありがとうございます。
アクセスされたWebサイトは 2023年3月31日を持ちまして閉鎖しました。
リンクを張っていただいている方は、お手数ですが設定を削除していただきますようお願いいたします。
今後とも「青天の霹靂」をどうぞよろしくお願いします。